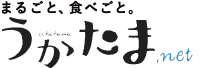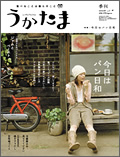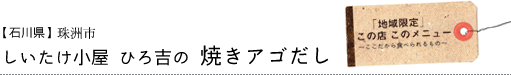
珠洲は、能登半島のさきっちょの日本海沿いの町。新鮮な魚や海藻から、米、大豆、しいたけと食材はふんだんにある。その食材を引き立てるのがアゴだしだ。アゴとはトビウオのこと。 海岸沿いの駐車場で、そのアゴの焼き干しづくりが始まっていた。
写真=富井昌弘 文=中田めぐみ

「ひろ吉」の夕食は輪島塗りの漆器に供される。手前右は、枝豆をすりつぶして味噌汁に加えた能登地方の料理「すりわり」。その奥が焼きアゴの酢の物。左は炊き合わせ。その隣、アゴの卵の煮付けは、とれたてのアゴが揚がる珠洲だからこそ、食べられる逸品。焼き魚はタナゴ
漁家では当たり前だった焼き干し
アゴの焼き干し、焼きアゴは6月から7月の間しかつくれない。
「この時期を過ぎると脂がのっちゃうのよね」と説明してくれるのは、珠洲で唯一の農家民宿「しいたけ小屋 ひろ吉」をやっている奥野文恵さん。
「うちのおじいちゃんが漁師で、昔は冷蔵庫もなかったから、とれたアゴは囲炉裏で焼いて柱に干してたそうよ」というのは新谷吉江さん。文恵さんも吉江さんも、地元の加工グループ「長手崎すいせん工房」のメンバーだ。
 |
奥野文恵さんとご主人の弘吉さん |
吉江さんの家では囲炉裏がなくなっても、練炭を使って焼きアゴづくりを続けていた。なぜそこまでしたかといえば「おいしいから」。焼きアゴは、みんな自家用でつくっていたものだから、店で手に入らない。となると、自分でつくるしかなかった。すいせん工房の前身は婦人会の料理クラブ。その活動のなかで、何か珠洲の海でとれるもので加工品をつくろうということになり、吉江さんが焼きアゴを提案した。このおいしさをみんなに伝えたいという思いもあってのことだ。
一方、文恵さんは、生まれも育ちも珠洲なのに、焼きアゴのだしの味はすいせん工房に入って初めて知った。これが「食べてみたらおいしかったのよ」というわけだ。漁家では当たり前と思われていただしの味なのに、同じ地元でも知られていない。「まずは地元の人においしさを知ってもらおう」と、焼きアゴは市内の直売所やAコープなど地域の人が買いやすいところにおいてもらっている。
煮干し? 焼き干し?
 |
乾燥機から出し、1尾ずつ丁寧に背骨をとる |
ところで、煮干しと焼き干しって何が違うの?
「煮干しは煮て干したもの。焼き干しのほうが手間はかかるのよ」と文恵さん。
まず、近くの蛸島漁港に揚がったアゴを朝仕入れて、その日の午前中には焼きあげる。1尾ずつ、頭を下ろし、ウロコを取り、はらわたを出す。下処理したアゴは串に刺し、珠洲特産のコンロ、珪藻土の七輪で焼く。焼きあがったアゴは、1日乾燥させ、そこで背骨を取り、また乾燥機に10時間かけてやっと完成。
途中、「焼きたてを味見してみたら」とすすめられたのだが、1尾ごと手間暇かけて焼いている様子を見てしまうと、もったいなくてつい遠慮してしまった(ちょっと後悔)。
煮干しとの違いはもちろん味もある。焼き干しは余分な脂が落ちて生臭みが少ないそうだ。
「煮干しは身が硬いけど、焼き干しはだしをとったあとの身も軟らかくて、ほぐして炊き込みご飯にしても食べられるのよ」と吉江さん。なるほど。しかも、頭もはらわたも背骨もとってあるから簡単に使える。「だし」と思うから贅沢品なのだが、焼いて干した保存の利く魚と考えると、もっと手軽に使えそうな気がしてきた。
焼きアゴで伝える珠洲の味
その焼きアゴだしを使ったそうめんを文恵さんの民宿「ひろ吉」でいただいた。
かつおだしの香りとは違うし、確かに普通の煮干しのような生臭さ、魚臭さがない。すっきりしていて、そうめんといっしょにスルスルとのどに入っていき、だしも全部飲みきってしまう。夏の食欲のないときでも、このアゴだしのそうめんなら、いくらでも食べられそう。